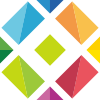昨今、医療機関の競争は「診療内容」だけでなく、「患者体験(PX:Patient Experience)」にまで広がっています。他業種においては「ユーザー体験(UX:User Experience)」ともいわれるもので、特に、Webサイトを通じた第一接点での印象がその後の関係を大きく左右します。
仮に予約しようと思った自院のWebサイトの予約がわかりにくかったり、操作が難しかったりすると、ユーザーインターフェイス(UI:User Interface)が悪く、診療内容に自信があったとしても、サイトやクリニックの印象を悪くしてしまうこともあります。
それゆえ、予約から診療後まで一貫した良質な体験を提供できるWebサイト設計は、医療機関が差別化を図るうえで極めて重要です。
この記事では、医療機関における患者体験を改善するための、患者に寄り添ったWeb UX/UI設計のポイントを分かりやすく解説します。
目次
患者目線で考える導線設計 ― 予約体験のスムーズ化
患者体験を向上させる第一歩は、予約導線をシンプルにすることです。
初めて来院する方でも迷わず操作できるよう、トップページに「予約はこちら」ボタンをわかりやすい位置に配置し、クリックから所要時間や受付方法を明示します。
具体的には、
-
電話・オンライン予約の選択肢を見やすく並べる
-
希望日時選択→確認→完了の3ステップ構成にする
-
スマートフォン最適化により片手操作で完結できるようにする
これにより、患者の不安や疑問を事前に軽減し、オンラインでの離脱防止にもつながります。
UX改善を意識するなら、予約完了画面に「確認メールを送信しました」「当日受付QRコードを発行しました」など、「受付でこれを見せれば間違いないな」と思えるメッセージを添えて安心感を与える設計も有効です。
診療前~診療後まで一貫した案内設計
Webサイトは予約後にも重要な役割を担います。診療前後の情報提供を一貫して行うUX/UIは、患者の安心感と信頼につながります。
診療前:
問診票ダウンロード/オンライン記入フォームを用意し、来院前に事前記入を促します。
LINE公式アカウントによる問診票も有効です。
また、アクセス地図や駐車場、交通機関など来院案内を視覚的に分かりやすく掲載しておきます。
よくある質問(FAQ)セクションを設け、診療の手順や持参物、服装、キャンセル規程などを丁寧に説明しておきましょう。
診療後:
次の予約や再診をスムーズにしてもらうために、予約ページへのわかりやすいリンクを記載するのも効果的です。
診療後、処置後の注意事項も書いておきます。
薬局との連携によって、処方薬の説明・副作用情報などの追記があれば、より丁寧な案内につながります。
アンケートやフィードバック機能を配置し、患者が感想や改善点を伝えやすい仕組みを提供しておきます。
このように、診療前から後までWebサイト全体で患者とつながる体験を設計すれば、クリニックの信頼性と品質感が高まり、「患者体験」がより豊かなものとなります。
UX /UIの差別化要素でブランディング強化
競合クリニックとの差別化には、デザインや機能面でのこだわりが大きな武器となります。以下のような工夫が有効です。
カラー設計とトーン設定:
自社のコンセプトに合った安心感を与える色づかいや、温かみのあるフォント、アイコンを併用することで、患者が落ち着いて読み進められるでしょう。
安心を演出するスタッフ紹介の動画導入:
スタッフ紹介や診療風景の短い動画を掲載することで、Web上でも“院内の雰囲気”を感じられるようにして、来院前に良いUXを与えます。
インタラクティブなコンテンツ:
例えば「症状チェック診断」や「費用シミュレーション」など、患者自身が参加して体験できる仕組みを導入すると、関与度が高まり信頼を強化できます。
アクセシビリティ対応:
高齢者や視覚に不安のある方にも配慮した、文字サイズ変更・音声読み上げ対応などの設計があると、より親切です。
サイト構築の手数はかかりますが、こうした差別化機能は、結果として「競合他院との違い」を印象づけ、地域や専門診療分野におけるブランド価値を高めることにつながります。
まとめ
医療機関のWebサイト設計においては、患者の立場に立ったUX/UI構造を整備することがポイントです。シンプルで直感的な予約導線、診療前から診療後まで一貫した案内設計、デザイン・機能面での差別化を行うことで、医院独自のブランドが構築されていくでしょう。
UXをより良いものへ見直すことで、クリニックは「ただ診療を提供する場所」から、「患者にとって安心・信頼できる体験を届ける場所」へと進化します。
Webサイトを通じて患者に寄り添い、地域や分野で選ばれる医療機関を作っていきましょう。